『モヤモヤの正体』(副題:迷惑とワガママの呪いを解く)
伊雄大(ユン・ウンデ) ミシマ社
コロナ禍自粛生活も1か月半…。ようやく京都も緊急事態宣言解除、という今日このごろですが、わたしはほっとする反面、まだこわごわな感じです。
ふだんはひとり遊びの得意なわたし。しかし、さすがにこの日々は奇妙な日常でした。
ついこないだも、つまらないことでイライラ、モヤモヤしている自分がいて、ふつうじゃないな…と気づきました。そのとき手に取ったのが、この本です。
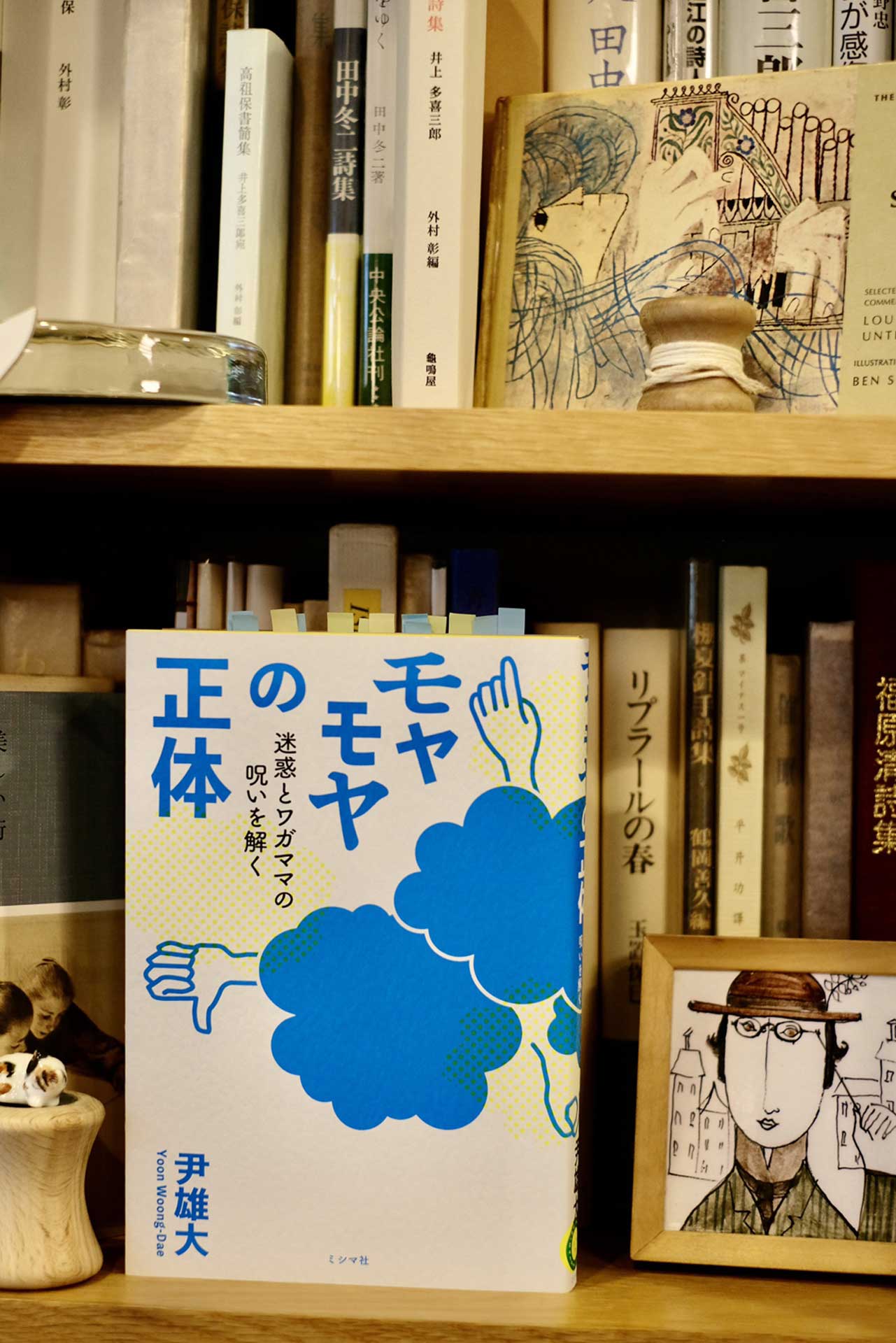
身の回りのことでも、朝のニュースでも、「なんだこれ」「あり得ない」と憤りを感じることがありますが、そのとき心に浮かぶのが、「べき論」。こうあるべきなのに、なぜあの人はこうしないのだろう? というような。
ここで自分が感じているモヤモヤ、イライラは、いったいどこから来るのでしょう?「べき」と考えている主体は、だれ?
「べき」の前には、たいがい「ふつう」がつきます。ふつうならこうするべき。ふつう…それは実は、「みんな」ということではないでしょうか。
みんなが迷惑している。
そんな思いがわたしたちをモヤモヤさせているのです。さてその「みんな」とは?
作者は、「みんな」とは、周囲の空気だと説きます。そして周囲の空気にのみこまれず、一度「みんな」という意識を自分の中から取り去ってみては、と提案します。
「みんな」を感じず、自分自身を感じ、観察し、自己否定にもおごりたかぶりにもならないように、ほんとうの自分(という主体性)にたどり着こうというのです。
こういう態度にいきつくと、人は互いに対立が生じても、その対立ははじまりになるだろう、と。
「互いに理解できないから行き止まりなのではなくて、その『理解できなさ』を巡って、しのぎを削ることが大事」
と述べています。
そうなんです。わたしたちは互いに、たやすくはわかりあえない。いやむしろ、わからなくてもいいのです。ただ、そのわかりあえなさいを通じて、互いにわかりあおうと努力すること、歩み寄っていくことが、たいせつななのです。
そんなふうに考えるきっかけになるのなら、モヤモヤもまた、捨てたものではないなあ、とわたしは思ったりしています。
写真・文/ 中務秀子
